|
忘れたくないこと---古来日本人がもっていた、目に見えないものに対する畏れと敬い。
|
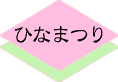 |
|
《雛の国見せの風習》
かつて雛人形を携えて野山に出かけるという風習がありました。人形に魂を見出し、上座に設えて共に 飲食を楽しみました。ひな飾りに桃の花や菜の花を供えるのは、野外での行事の名残りでしょう。 また桃は、中国では、不死の薬を持つ西王母が、長寿を願う漢の武帝に仙桃を与えた伝説があります。 日本の古事記には、いざなぎの尊が、黄泉の国から追いかけてきた妻のいざなみの尊から逃れるために、 桃の実を投げて助かったという神話があります。霊力のあるものと考えられていたのですね。 |
|
《擬死再生のストーリー》
人形に穢れを移して海や川に流す「流し雛」の風習は、水に流して再生を願う「擬死再生」という 考え方があるといわれます。 神前でかしわ手を二つ打つのも、一つで死んで穢れを落とし二つ目で再生を祈るという、尤も簡便な擬死再生の 形ともいわれています。(心して打たねば…) |
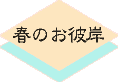 |
|
春分と秋分とを中日として、その前後三日ずつ七日間をいいます。生死流転に迷う此岸(この世)に
対して、煩悩の流れを超えた悟りの境地を彼岸といいます。 「暑さ寒さも彼岸まで」といわれる季節で、農業国の我が国では、農事の目安にしたりそれに伴う 神事が行われます。また、山遊びや野遊び、磯遊び等信仰を離れた行楽が盛んです。 |
|
山辺には たらの芽を摘む彼岸かな 白 雄 山寺の扉に雲遊ぶ 彼岸かな 蛇 骨 |
|
《彼岸だんごとぼたもち》
家々でだんごやおはぎをつくって先祖の霊に供え、共に食する風習は今でも行われ、町のお菓子屋さん で購うことが普通になりました。 おはぎ(春は牡丹餅といいます。)初代川端道喜が時の禁裏に献上した 「御朝物」は、いわゆる萩の餅、おはぎであったそうです。 |
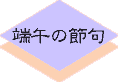 |
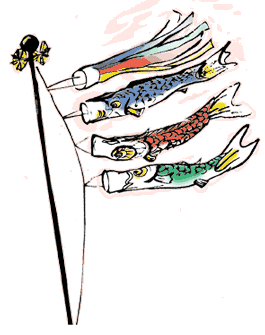 |
|
「端」は初めの意味。「端午」は月の初めの午の日。 奇数が重なることは本来は悪いことが起き易い日という ことで、この日は厄除けの日だったということです。 又、五月五日は田の神様の降臨の日で、家々で長い 竿に吹き流しをつけて、神様への目印にしたとか。 《吹き流し》 青、白、赤、黒、黄の五色。「五常の心」 即ち仁、義、礼、智、信の心を表わします。 |
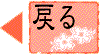
|