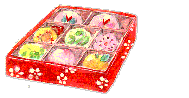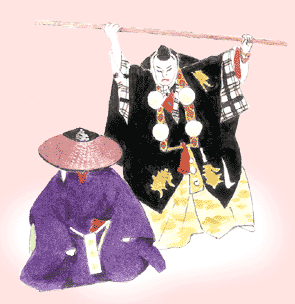|
草木の芽が「張る」(はる)田畑を「墾る」(はる)。「晴る」とも。 勢いの盛んな時。得意な時。 |
|
二月〈如月〉きさらぎ
|
寒くて更に衣を重ねる。 春まだ遠い。 |
|
三月〈弥生〉やよい
|
いやおい。いよいよ草木が勢い盛んになる。 雛月、春惜月 |
|
四月〈卯月〉うづき
|
卯の花が盛んに咲く月。 作物の植月とも。 |
|
五月〈皐月〉さつき
|
早苗月の略ともいわれているが「サ」というのは「田の神」
に関するらしく「田の神の月」ではないか? サナエは早苗ではなく「田の神の苗」の意味と思われるとか。 |
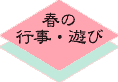 |
寒 梅・お彼岸・ひな祭・摘み草 |
 |
変化のある豊かな気候風土が、趣きのある雨の名前を生みました。 |
|
◇雨の名前(小学館-「雨の名前」から)
|
|
|
甘 雨 (かんう)、 慈 雨 (じう)、
紅 雨 (こうう)、 木の芽雨(きのめあめ) 花時雨(はなしぐれ)、 菜種梅雨(なたねづゆ) |
|
◇地方に伝わる珍しい名前
|
|
蛙目隠し---(新潟県東蒲原郡)想像してみて下さい。・・・
麦食らい---(高知県長岡郡)麦の穂がでる頃に降ってその生育を害する雨 じぼたら雨---(和歌山市)じめじめ降り止まない雨 |
|
降るとも見えじ春の雨 水に輪をかく波なくば けぶるとばかり思わせて 降るとも見えじ春の雨 (文部省唱歌 四季の雨) |
| 花の里心も知らず春の野に いろいろ摘める母子もちいぞ 和泉式部 草餅を作るために母子草を摘んでいるようすです。 草餅は、蓬で作るもの思っていましたが母子草で できるとは、知りませんでした。 中に入れる小豆餡は鎌倉時代以後だということです から単に草を搗き込んだお餅ということでしょうか。 |
 ははこぐさ ははこぐさ春の七草の一つ、ごぎょう(おぎょう)とも。 |
||
|
◇お店に並んだ春の和菓子は、どれも可愛らしくて季節感がいっぱいです。
|
|||
|
上生お重 菱餅(五段重ね三段重ね)
|
|||
|
紅梅匂 桜重ね 青 柳 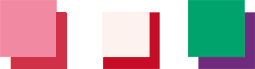 紅/蘇芳 白/紅 緑/青紫
|
|||
|
お祝の祝儀袋(たとう)を、色襲ねを参考に創ってみては如何ですか。
|
|
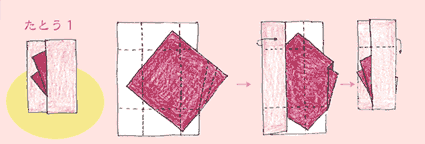 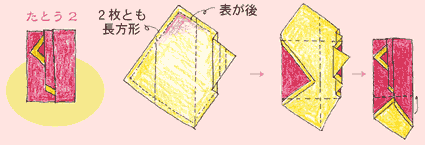 |
| 江戸好み 歌舞伎の舞台を彩る華やかな色調は、庶民の日常を乗り越えて時代の感覚が つくり出した究極の色彩世界です。 |
 |
|
|
花四天---捕方(四人)
捕方(警官隊や機動隊員)を ここまで風流にしてしまう |
勧進帳の弁慶と義経 |
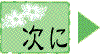 |