そこで「秋」といえば、秋空 −柿の梢の鈴なりの実− −柿羊かん− −香りのよいお茶− −しまい忘れの風鈴......
いろいろありますが、まずは柿のことから。
| この季節の事を、古代の人はどうしてアキと言ったのでしょう。早速、広辞苑を引いてみますと、一説に、空が清く、明らか(あきらか)になる季節だからか...とありました。なるほど...... そこで「秋」といえば、秋空 −柿の梢の鈴なりの実− −柿羊かん− −香りのよいお茶− −しまい忘れの風鈴...... いろいろありますが、まずは柿のことから。 |
 |
平安の頃、柿といえばまだ渋柿でした。 |
|
| けれど王朝の風雅な歌人は鄙びたその実よりも 紅葉した葉の美しさを好んだようです。 実際、驚くほど美しいですね。 |
 |
|
| (秋の絵手紙には最適) | ||
 |
カキは日本の色名ですが、外国でもKAKIです。 |
|
| ところで、これは余談ですが、中世の頃は、 アウトローの色とされていたこともあります。 雨月物語の白峯に、 「柿色のひどくすすけた色の御衣」をまとった 崇徳上皇のお姿...とありますが、 上皇は既に幽界の怨霊となった方です。 そんなことで中世の日本人の色彩感覚の中に、 暗い柿色は異端の色だったようです。 |
 歌舞伎の幕 |
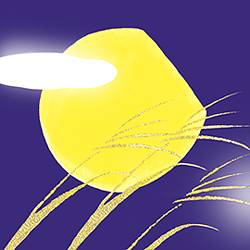 |
美しい秋の言葉〜歳時記より〜 |
| 待宵(まちよい)・・・・宵(月の出)を待つ心 | |
| 草紅葉(くさもみじ)・・小さな草々の紅葉 | |
| 月の船・・・・・・・・船の形になった三日月 | |
| 夜長・・・・・・・・・しみじみと長い秋の夜 | |
| 笑栗(えみぐり)・・・・イガがはじけて微笑んで見える栗 | |
| 色無き風・・・・・・・澄明な寂しい秋の月 |
![]()
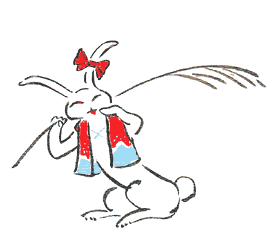 |
お月見 | |
| 陰暦8月15日の月が一番美しいとされる中秋の名月。 秋の収穫物を月の神と共に食するという風習。 |
||
| 秋の彼岸(秋分の日) | ||
| 秋分の日9月23日前後7日間を彼岸といい、秋分の日が中日。 おはぎを供えたり墓参りに行ったりして先祖を偲びます。 |
||
| 衣更え | ||
| 10月1日、薄物から厚めの衣服に替えます(夏服→冬服の制服) | ||
| 敬老の日 | ||
| 9月15日 この日に限らず敬老の心をいつでも持っていたい ものです。 |
||
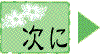 『秋』次のページへ→ |
 おはぎ |
![]()
〒111-0036 東京都台東区松が谷3-21-7 ローザス・フジ1F
TEL:03-5806-3388(代) FAX:03-5806-3466
e-mail : info@taiko-do.co.jp